日本で一番重い罪
突然ですが、日本で一番重い罪は何でしょう?
…答えは「外患誘致」です。
刑法第81条に規定があります。
刑法 第81条
刑法
外国と通謀して日本国に対して武力を行使させた者は、死刑に処する
法定刑が死刑しかありません。
外国政府と手を結んで日本国を武力攻撃してしまったら、減刑がない限り確実に死刑になってしまいます。
「外国と組んで日本を攻めるのは仕方なかったね」と酌量減刑が認められることはほぼないでしょう。
なので、政治に不満があるからと言って、外国政府と手を結んで武力攻撃するのはやめておきましょう。
ちなみに現在のところこの刑が適用された事例はありません。
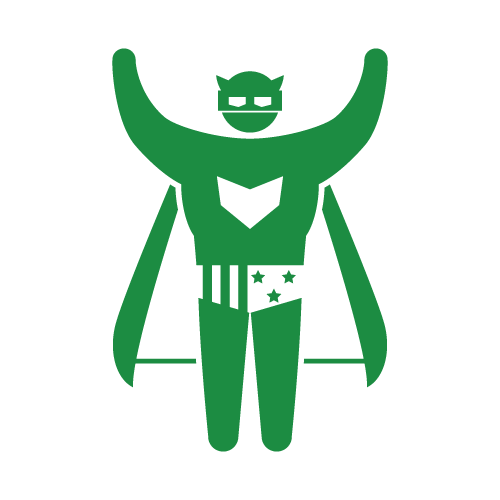
軽車両の範囲
道路交通法に軽車両の定義が書かれています。
道路交通法 第2条
道路交通法
11項 軽車両 次に掲げるものであって、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車輌に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)
というわけで、牛も馬もそりも道路交通法上は自転車と同じ軽車両に分類されています。
なので、馬で公道を走る際は運転免許証は不要ですが、車道の左車線を走る必要があります。
赤信号ではきちんと止まる必要があります。
他のドライバーからの視線が気になっても逃げてはダメです。
通常、馬にウインカーはついてないので、手信号をしてください。
お酒を飲んで馬で走ったり、公道でそりに乗ると飲酒運転になりますので、飲酒後は乗らないようにしましょう。

元号に関するルール
2019年5月1日に元号がそれまでの「平成」から「令和」に変わりました。
当時は次の元号予測や、天皇即位に伴う10連休で世間がとても盛り上がりましたね。
ところで、この元号を規定する法律はどうなっているのでしょうか?
元号法
元号法
1.元号は、政令で定める。
2.元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附則
1.この法律は、公布の日から施行する。
2.昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
以上が元号法の全文です。
附則の2条は、この法律ができたのが昭和54年だから付け加えられたものと思われます。
昭和の元号も適法に定められたことにするための規定です。
「元号は皇位の継承があったときのみ政令で決める」ルールはこれだけです。
日本の法律の中でもトップクラスに短い法律です。(※トップではありません)
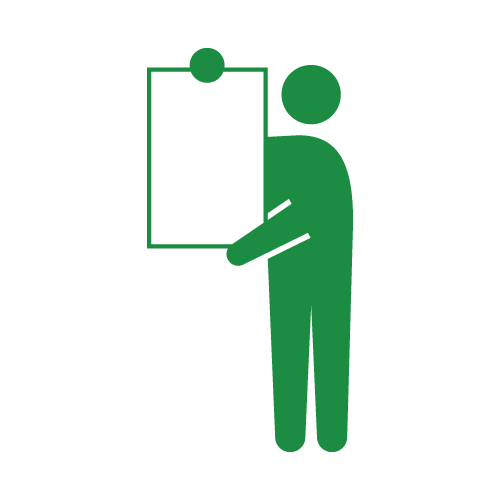
紙幣と貨幣の発行元
日本で今現在使われている通貨として、紙幣(お札)と貨幣(硬貨)があります。
この2つは実は発行元が違います。
日本銀行法 第1条
日本銀行法
日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。(※注 銀行券というのが現在日本で使われている紙幣のこと)
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第4条
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
貨幣の製造及び発行の機能は、政府に属する。
日本銀行は国家機関の一つではなく、独立した法人です。
日本銀行が紙幣を発行し、日本政府が貨幣を発行するというのが現在の日本の仕組みです。
お持ちの紙幣と貨幣を見比べてみてください。
紙幣には「日本銀行券」と、貨幣には「日本国」と書かれています。
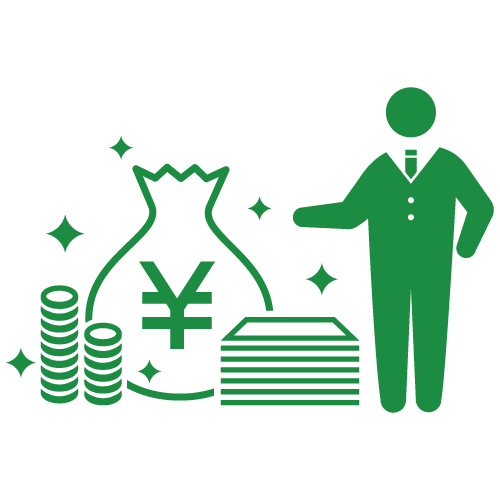
日本の国旗についての法律
日本の国旗は「日章旗」です。
日の丸のことですね。
これが正式に決まったのは平成11年8月13日です。
意外とつい最近の出来事です。
それより以前から色んな所で使われてはいましたが、正式に日本の国旗として定められたのは約20年前のことです。
例えば、江戸幕府は日本船の旗印として日章旗を使用していました。
さらにその前、現存する最古の日の丸の旗は、戦国最強と言われる武田信玄で有名な甲斐の武田家に伝わっていたものだそうです。
なお、太陽を赤色で表現するのは世界的にも珍しいらしいです。
日章旗は制式が決められていて、縦は横の3分の2、直径は縦の5分の3、色は白地に紅色と規定されています。
これには特例があります。
国旗及び国歌に関する法律 附則
国旗及び国歌に関する法律
3 日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる
難しい表現で何を言っているのかマジでわかりません。
ですが、日の丸の中心を旗竿側に100分の1ずらすのはOKと書いてあるようです。
そのレベルの位置の変更は、細かすぎて肉眼で判別するのは難しそうですね。
蛇足ですが、法律には「当分の間」という言葉は結構出てきます。
法律の勉強をされている方の中には、「当分の間」が終わっているんじゃないかと思って毎年チェックされている方もいませんか?
ですが、ほとんどの条文の「当分の間」は長年続いたままになっています。
こんなに長く続くのならわざわざ入れなくてよかったのにと思うほどです。

敬称に関する法律
「天皇陛下」、「皇太子殿下」などの言葉をニュースではよく耳にすると思います。
実はこの陛下、殿下という敬称は法律で決まっています。
皇室典範 第23条
皇室典範
1.天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
2.前項の皇族以外の敬称は、殿下とする。
太皇太后とは当代の天皇の祖母(先々代の天皇の正妻)のことで、皇太后とは先代の天皇の皇后であった人のことです。
(なお、近年復活した称号である「上皇」、「上皇后」に対しては「陛下」の敬称が使われることが特例法によって定められました。)
「陛」とは宮殿の階段のことで、「陛下」とは階段の下を意味します。
帝に上奏する者が、陛の下にいる臣にその内容を告げて、代わりに上奏してもらっていたことに由来する言葉です。
殿下は摂政や関白に対しても使われたそうで、時代劇や大河ドラマで豊臣秀吉(関白)が殿下と呼ばれるのはこのためです。
皇族ではない人に対して使われる敬称として、「閣下」というものがあります。
国家元首や戦前の陸軍将官に対してよく使われていたそうです。
けどこれは、「バイデン大統領閣下」よりも「デーモン小暮閣下」のほうが圧倒的にしっくりきますね。
さすが10万58年の歴史を感じます。ちなみに閣下は広島東洋カープのファンだそうです。



